目次

若松 優津(わかまつ・ゆず)
1995年東京都生まれ。AFBB、東京scratchgirl所属。
小学生の頃に感音性難聴と診断を受け、補聴器を付けて生活する。バスケは小学生から始め、高校は千葉英和、大学は江戸川大学といずれも強豪校に進学。
社会人になってデフバスケに出会い、29歳で東京2025デフリンピックのデフバスケ女子日本代表に選出。2024年にオーストラリア・メルボルンで開かれた「アジア太平洋ろう者バスケットボール選手権大会」ではポイントガードとしてチームをけん引し、優勝に大きく貢献した。大会MVPにも輝き、来たるデフリンピックでの初の金メダル獲得に意欲を燃やす。
受け入れられなかった“デフ”との出会い
――バスケを始めたきっかけを教えてください。
小学生の頃、友達に誘われてミニバスのクラブチームの練習を見に行ったのが最初です。初めてボールに触ってみたらとても楽しくて、その場で「やりたい!」と即決しました。学校外のチームで友達と一緒にバスケをすることも特別な感じがして、すごくうれしかったんですよね。
――小学生の頃からバスケ一筋だったんですか?
そうですね。地元が足立区の宮城というところなんですが、中学校は強いチームでやりたかったので、学区外の足立九中に行きました。毎朝長時間のバスと電車を乗り継いで通っていたので、今考えると中学生にしてはかなりの大移動でしたね。でも日々の練習は楽しく、のめりこみながら成長できたこともあって、チームも結果を出し、個人としても東京都選抜に選ばれるなど評価していただけた時期でした。その流れで高校も強豪の千葉英和高校に進学したんです。

とにかくバスケを楽しんでいた。
――その頃からすでに、将来はバスケでやっていきたい気持ちがあったのでしょうか。
それもありましたし、足立九中時代の同級生(今年プロを引退した星香那恵選手)と一緒に千葉英和に声をかけてもらえて。ありがたい機会だったので、チャレンジしてみたいと思いました。
――デフバスケに出会ったのはいつ頃ですか?
大学に入ってからです。江戸川大学という厳しい練習で有名な強豪に進学しました。難聴のことがあったので、あるときトレーナーから「デフバスケに挑戦してみない?」と言われたんですが、当時はそのことを前向きに捉えることができませんでした。というよりすごく腹が立って・・・。「このチームに私は必要ないってことですか!?」と食ってかかったくらいだったんです。
――どうして、そんな反応に?
もちろんトレーナーは、私の耳のことを気遣っての提案でした。でも当時は、自分が難聴であることも受け入れ難く、障害者手帳を持つことにも躊躇していました。今思えばもっと早くデフバスケに挑戦しておけばよかった・・・と思うのですが、ちょうど敏感な年頃でピリピリしてしまって、トレーナーの言葉に耳が貸せなかったんです。

――そうだったんですね・・・。難聴であることはいつ頃わかったのですか?
小学生の頃です。健康診断の聴力検査で高い音が聞こえていないと言われて、そのときに初めて感音性難聴であることがわかりました。おそらく笛の音などがかなり聞こえにくかったと思うんですが、自覚は全くなかったんです。現に高校生までは聞こえにくさでプレーに困ることもあまりなく、補聴器を付け始めたのも社会人になってからです。
――ということは、手話もここ数年で覚えたんですか?
3年ほど前からですね。独学で始めて、チームのみんなに教わりながらなんとか身に付けていって。ようやく手話でもコミュニケーションが取れるようになってきましたね。
――現在は聴者の社会人クラブチーム『AFBB』と、デフバスケの『東京scratchgirl』の両方に所属されています。学生時代にデフバスケへの挑戦に踏み切れなかった中で、どのような経緯があったんでしょうか?
大学を卒業してから実業団チームに2年ほど所属していたのですが、その後同じリーグ内のAFBBに移籍しました。対戦していてもすごくいいチームでしたし、知り合いもいたのでいろいろ話を聞いたり、練習に参加してみたところ、想像以上に魅力的なチームで。そこで自分から志願して移籍したんです。
その後、AFBBの先輩にお子さんが生まれたのですが、その子が重度難聴だったんです。それまでの人生でろう者と接する機会がほとんどなかった私にとって、衝撃が大きかったですし、すごく刺激になったというか・・・勇気をもらったような気がしたんです。
同時に、自分の聴力も学生時代より落ちてきていて、『デフ』という現実と向き合う機会が増えていました。そんな中で、初めて「デフバスケに挑戦してみたい」という気持ちが芽生えたんです。そこで大学時代のトレーナーに連絡を取って、デフバスケの日本代表選考会を紹介してもらいました。

日本代表選考会で出会ったメンバーも多く所属している
――AFBBには、若松選手以外にもデフバスケの日本代表選手が所属されていますよね?
そうなんです。丸山香織選手と川島真琴選手です。二人とは2022年の日本代表選考会で出会いました。よりスキルを磨くためにはレベルの高いチームで練習できた方がいいですし、その経験がデフバスケにも還元されます。その考えをAFBBの監督が汲んでくれて、二人も受け入れてくれました。AFBBはデフバスケ日本代表と強化試合を行ってくれたりと、とても理解のあるチームなんです。


現在はデフバスケ日本代表が3名所属する
静寂の中でのチームプレー
――デフバスケを始めたときに、聴者のバスケとの違いに難しさを感じた部分はありましたか?
一番はコミュニケーションですね。例えば「スクリーン」という、味方が壁になってディフェンスの動きを邪魔するプレーがあります。この壁役のプレイヤーはディフェンスの背後など死角から現れるので、聴者のバスケでは、仲間のディフェンスにスクリーンが行ったことを大声で知らせるんですね。それで、ディフェンスは背後に気付いてスクリーンを避けることができるんです。
でも、デフバスケの場合は後方からの声かけが伝わりません。バスケを見たことがある方ならわかるかもしれませんが、聴者のバスケってひたすら声をかけ合っているんですよ。それでチームプレーが成立しているんです。でも、デフバスケではその声が届かない。最初はそこが本当にもどかしくて、難しかったですね。
聴者のバスケでは練習でも試合でも「とにかく声を出してコミュニケーションを取れ」と言われてきたので、それが全くできないとなると、“別物のスポーツ”と言えるくらい違いました。
――デフバスケの場合、どうやって合図をし合うんですか?
味方の視覚に入っていれば手話で合図するんですが、見えていないときは足でドンドンと床を叩きます。体育館だと振動がよく響くので、それで「何かある」と気付けるんです。距離が近ければ肩などを触ったり、軽く押したりして合図することもあります。
――手話といっても、バスケのように動きの激しいスポーツだと容易ではないですよね・・・?
そうですね。例えば手話で「リバウンド」と伝えたいときに、指文字でやるとすごく長くなってしまうので、オリジナルの簡潔な手話を決めて、チームで共有したりしています。試合中はほぼ動いているので一瞬で意思疎通しないといけないので、いかに簡潔な手話で瞬時にコミュニケーションを取り合えるかがとても重要なんです。

――「サインバスケ」という言葉も耳にしますが、また手話とは違うんですか?
はい、手話とはまた違う手の動きで、みんなが同じプレーをイメージできるようにつくられたのがサインバスケ。日本語でも手話言語でもなく、バスケに特化した視覚言語です。共通言語にできれば、きこえてもきこえなくても、言語の違う外国人とも一緒になってバスケを楽しめるんです。サインバスケがもっと広がるのが理想ですが、まだまだ知られていないのが現状ですね。
――デフバスケの試合中に、若松選手が心がけていることはありますか?
私はポイントガードというポジションを担当しています。チームに指示を出して得点に導く役割なんですが、声がない分、より的確に簡潔に指示する必要があります。だからとにかく周りを見て、冷静な判断ができるように意識しています。
あとは仲間としっかり目を合わせることですね。デフバスケではアイコンタクトが命。苦しい展開になると下を向いてしまいがちですが、それはデフバスケでは致命的です。だからこそ練習から、常に顔を上げて目を合わせることを心がけています。
――今回のデフリンピックで初めてデフバスケを観戦する方もいると思います。どんなところに注目して見ると試合をより楽しめますか?
聴者のバスケしか見たことがない人からすると、シーンと静まり返ったデフバスケ特有の雰囲気にまず衝撃を受けると思います。実際に私がそうでした。選手同士の声かけがないので、静かな空間にシューズのキュッキュッという音や、シュートの決まる音だけが響き渡るんです。これはぜひ体感してみてほしいです!
そしてスピード感あふれる展開の中で、選手同士がどのようにコミュニケーションを取っているか。そこにも注目して見るとおもしろいと思います。余談ですが、私は聴者の試合でもつい癖で足をドンドンしてしまって。相手から「あの人キレてる」と勘違いされることもあって、その状況に我ながら笑いそうになるときがあります(笑)。

「悔しさ」を原動力に。訪れた挫折の日々
――若松選手のプレーの強みはどんなところですか?
自覚している強みは、オフェンスよりもディフェンスです。アグレッシブにプレッシャーをかけることで、相手に流れを渡さない展開をつくる。そこが自分の持ち味だと思っています。これまでもディフェンスを評価されて、大事な場面で出してもらえることが多かったです。反対に・・・ポイントガードは向いてないと降ろされたこともあるんです(苦笑)。それでも持ち前のスピードを活かして試合の流れをつくることを心がけていて、デフバスケではポイントガードとして貢献できるようになってきました。
――小学生の頃からバスケ一本でやってきて、辞めたいと思ったことや挫折の経験などはなかったのでしょうか?
もう、ありまくりです(苦笑)。中学生までは主力でプレーし東京都選抜にも選ばれていたのですが、高校からは挫折の連続で・・・。決して楽しい記憶ばかりではないですね。バスケが好きだから続けられてきたのはもちろんですが、「もっと認められたい」という悔しさをバネにしてきた部分の方が大きいです。
――原動力はそっちなんですね。
強豪校だったので県選抜のメンバーばかり入ってくるようなところで。初めてメンバー落ちを経験して、ユニフォームをもらえなかったんです。それが本当に悔しくてショックでした。翌日から遠征だったのですが、家に帰って泣いて泣いて泣きまくって、パッキングもしないまま寝ましたね・・・。結局目をパンパンにして行ったのですが、そのときの悔しさは今でも忘れることができません。
当時から点を取るのはあまり得意ではなかったのですが、それでも積極的にトライして必死にアピールしていました。だけど、なかなかメンバーに入れなかったり、入れてもプレータイムが伸びない日々が続き、結局は実力の世界なんだと思い知りましたね。「辞めた方がいいのかな」と何度も考えました。

――高校でしっかりプレータイムがもらえるようになったのはいつ頃ですか?
要所要所、大事な場面でも使ってもらえることもありましたが、思っていたよりもプレータイムが伸びなかった3年間でしたね・・・。3年生のときに、私たちの代が初めて12月のウインターカップ(全国高等学校バスケットボール選手権大会)に出場したんですが、3年生は受験もあるので、引退せずに残るかは自主的に決めていいと言われたんです。そのときに、10人くらいいた3年生のうち私を含め3人しか残りませんでした。それで、引退するまでのわずかな期間でしたが、やっとしっかりしたプレータイムがもらえるようになりました。
――高校で挫折を味わったときは、どのようにして乗り越えたのでしょうか。
もう「やるしかない精神」です。結局は頑張ること以外何の解決策にもならないですし、私のキャラ的に、辞めたら辞めたで絶対に後悔していたと思います。
それと・・・母の存在も大きかったですね。「大事なのは試合に出ることだけじゃなく、何をやったかどうかだよ」と結果ではなく過程に価値を見出してくれて、本当に救われました。母は何かあっても、「泣いてても仕方ないじゃん!」と明るく言ってのけるようなタイプなんです。考え方の面でいちばん影響を受けてきたのが、おそらく母ですね。まあ、喧嘩もめちゃくちゃするんですけどね(笑)。
――肝の据わったお母さんですね。大学での活躍はどんな感じだったんですか?
大学でもやっぱりプレータイムを伸ばすことに苦労しました。その中で、4年生になったときに立候補してキャプテンをやったんです。ただ、自分がどのような状況だろうとチームに対して厳しいことを言わなければいけないのは、葛藤もあり辛かったですね。4年生のときは試合に出られない云々よりも、精神的なしんどさの方が上回っていました。
――なぜキャプテンに立候補しようと?
私たちが4年生になったときに、監督が海外にコーチ留学に行くというので代理のコーチが来たんです。でも監督の不在によって、選手たちに不安や戸惑いが生まれてしまって・・・。誰かがまとめなくてはいけない状況を見かねて、ここは自分がやるしかないと決意したんです。大変ではありましたが、私を慕ってついてきてくれる後輩もいたので、振り返るととても大きな財産になったと思います。

忘れられない試合のカギはいつも・・・
――いろいろなことを乗り越えてきた若松選手が、これまでにいちばん印象に残っている大会を教えてください。
まず思い浮かぶのは、高校のときのインターハイ県予選の決勝リーグです。インターハイに出場できるのは県内から2校だけなんですが、大事な試合を落として、かなり厳しい局面になってしまったんです。最後の試合で20点以上の差をつけて勝てばインターハイに行けるという状況で、相手もベスト4常連の決して弱くはない高校でした。正直、大差で勝つのは厳しい状況だったのですが・・・、必死に戦ってなんとか勝ち切ることができたんです。その試合ではディフェンスが鍵だったので、自分の強みを活かして求められた仕事を果たすことができ、自信につながった試合でした。
――デフバスケにかかわるようになってからはいかがですか?
昨年出場した「アジア太平洋ろう者バスケットボール選手権大会」(以下、アジア大会)の決勝ですね。このときは日本、オーストラリア、台湾の3ヵ国が出場したのですが、日本は決勝でオーストラリアに85対67で勝って優勝したんです。点差以上に接戦で苦しい時間帯もありましたが、諦めずに粘り勝てたことは日本代表にとって大きな意味がありました。

――しかもこの大会では大会MVPにも選出。日本代表の勝因はどのあたりにあったと思いますか?
オーストラリアの選手は190cm近い選手も多く、フィジカルの強さは圧倒的でした。その中で逆に小柄な体格を活かし、スピードでいちばん優れていたのが日本でした。さらにチームで決めていたことは、「攻めたディフェンスを徹底しよう」ということ。決勝では特にアグレッシブなディフェンスを仕掛けることができて、日本の流れに持っていけました。そこが最大の勝因だったと思います。

勝ち取った優勝
――若手の選手などは接戦の展開に焦りもあったと思いますが、どういう声かけを大事にしましたか?
オーストラリアはスリーポイントをバンバン決めていたので、焦りは確かに大きかったと思います。点を取られても、「大丈夫だから1本1本守ろう」と声をかけて落ち着かせていました。ただ苦しくなるとうつむいてしまって、チームメイトと目が合わなくなることもあります。でも、アイコンタクトこそデフバスケ。「ミスしてもいいから、顔を上げてしっかり目を合わせよう!」と試合中も強く伝えていました。
――オーストラリアのメルボルンでの開催だったそうですが、少しは観光も楽しめましたか?
はい、オフが2〜3日あったので、みんなでご飯を食べました。メルボルンは初めてでしたが、コーヒーがとっても美味しかったです。個人的にはアルコールも好きなんですけど、未成年の選手もいたので、優勝した日はコーラで乾杯しました(笑)。お土産ではしっかりオーストラリアのワインを買いましたよ。


嬉しさと緊張が入り混じる初のデフリンピック
――アジア大会はデフリンピックにつながるいいスタートになったと思います。日本代表には初選出となりますが、今の心境を教えてください
世界を舞台に戦う上で、やっとスタートラインに立てたという思いがあります。その一方で、プレッシャーも感じました。デフバスケにはこれまで長年築き上げられてきたものがあって、それに比べると私の経験はまだまだ浅いです。日本代表になったからには「結果を出さなければ」という責任感もあり、嬉しい反面、緊張もしているのが正直なところです。
――デフリンピックではどこを目指したいですか?
やっぱり金メダルです! これまで支えてくださった方々に恩返しするためにも、結果で示したいと思っています。
――強化していきたい課題などは?
自分の課題は得点力をもっと上げることです。アジア大会ではチームメイトを必死に鼓舞していましたが、実は私自身も海外選手の強さに気後れしてしまって、いい波に乗り切れなかった部分がありました。欧米の選手はさらに強いので、いかに点を取っていくかは今からしっかり対策してイメージしておく必要があります。
私は小柄なので、ドライブだけでは限界があると思います。だからこそスリーポイントのような外のシュートをもっと高確率で決められるように、残りの3ヵ月でしっかり磨いていきたいです。

――デフリンピックの先のビジョンはイメージされていますか?
まだ具体的には見えていませんが、デフバスケの魅力を伝える立場になりたいと漠然と考えています。私は小学生の頃に難聴がわかりましたが、デフバスケの存在は知っていても、触れる機会って全然なかったんです。だからこそ、ろうの子供たちがデフバスケに出会えるようなきっかけを作りたい。その上で、きこえなくてもスポーツで活躍できることを、自分の経験を通して伝えていきたいですね。
愛すべき地元、足立区宮城
――ここからは、若松さんのプライベートな部分についても聞かせてください。子供の頃はどんなお子さんでしたか?
何より負けず嫌いで、男勝りな性格でした。幼稚園のときの連絡帳に、「友達の腕を雑巾搾りして泣かせていました」って先生からのコメントで書かれてあったんです(笑)。小学生の頃もそんな感じで、母が謝って回ったらしいです・・・。
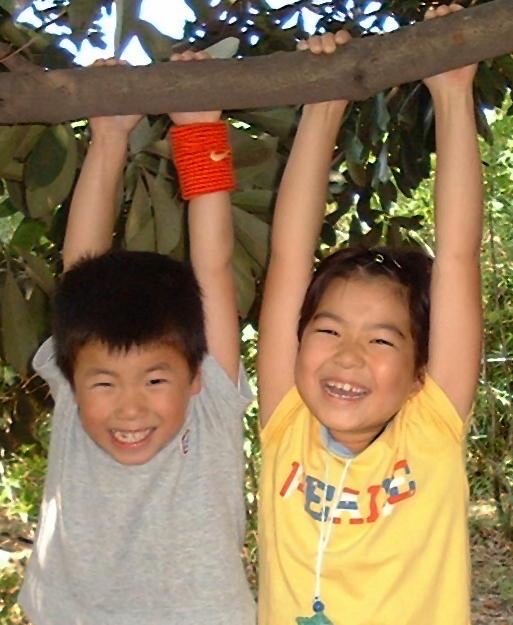
(右が若松さん)
――そうだったんですか!? 今の若松さんの笑顔からは想像できないですね。マイルドになったのはいつ頃ですか?
中学校までは男勝りでしたね。卒業式の合唱で指揮をやったんですが、ヤンチャな男子たちがちゃんと歌ってないと、「お前ら歌わないなら帰れ!」って言えるくらいの感じでした。高校に入ってからはだんだん丸くなりましたね。大人になったんでしょうね~。
――生まれ育ったのは足立区の宮城だそうですが、どんなところですか?
地図で見るとよくわかるんですが、ちょうど荒川と隅田川に挟まれた三角州みたいなところなんです。橋を渡らないと外の世界に行けない。隔離されているから文化が入ってくるのが遅くて、ひと昔前のものが流行るんですよ。だいぶ時期が過ぎた頃に「たまごっち」が流行ってました(笑)。
――え! 都内なのに?
はい、大袈裟じゃなく本当なんです! でもすごく自然豊かなところで、河川敷は開放的で本当に気持ちがいいですし、私はすごく好きな場所です。川に囲まれているので“謎のルール”みたいなものもあって、「小学校を卒業するまでは絶対に橋を渡るな」って言われて育ちました(笑)。だから卒業式の日にみんなで意を決して、プリクラを撮りに川を渡ったんです(笑)。
――へぇ〜〜(笑)。宮城、興味深いところですね。じゃあ足立九中に行ったのはかなりチャレンジングだったんですね。
ちょっとした「旅」でした。小学校も中学校も全部三角州の中にあるので、本当なら宮城だけで全て完結するんですよ。だから出ない子は本当に地元から出ないですね。もう小さい頃から町の人みんなが育ててくれるので、東京にしては人と人との距離が近くて、人情味のあるところです。機会があったらぜひ行ってみてください!

愛すべき足立区宮城を語る若松さん
仕事終わりのビールと唐揚げ
――バスケ以外で趣味や特技はありますか?
絵を描くのが好きです。小さな頃からよく似顔絵などを描いていたんですが、社会人になってタブレットを持つようになってからは、さらに頻繁に描くようになりました。犬の絵を描くのが好きで、LINEのスタンプにしたり、オリジナルのポストカードをつくったりもしています。


――本格的ですね。普段は仕事と競技を両立されているんですよね?
はい、仕事はKHDという電線のメーカーで営業をしています。営業の仕事はコミュニケーション力がひたすら求められるので大変ですが、おかげでしゃべりがうまくなってきた気もします(笑)。
日中は仕事をして、バスケは火・木・土・日が基本的にAFBBの練習日。不定期で東京scratchgirlの試合なども入ってきますね。週末はAFBBのリーグ戦もあったり、たいてい体育館にいますね~。幸せです。
――オフのときは何をして過ごすことが多いですか?
買い物など、出かけることが多いですね。試合がなければ美味しいものを食べに行って、お酒を飲んだりもします。月・水・金は仕事終わりに会社の近くで飲むこともあります。職場が東銀座なので、有楽町や日比谷界隈で一人で飲んでます(笑)。
――え、一人飲みなんですか!?
一人飲み・・・できるようになっちゃいました(笑)。サクッと一杯やって帰ることが多いですが、よくビール片手に唐揚げを食べています!
――わかります! 最高の組み合わせですよね(笑)。仲のいい選手と一緒に飲んだりはしないんですか?
イベントでデフ卓球の亀澤理穂選手と知り合って以来、何度か食事に誘ってもらって一緒にお酒も飲みました。亀澤さんもいける口ですね(笑)。デフアスリートとしていろいろな活動をされていて視野も広いので、すごく刺激をもらえます。ひたすら明るい方ですし、モチベーションが下がっているときに会うと特に格別です。

――料理もされるんですか?
それが料理はしないんですよ。先日かぼちゃのポタージュを作ったら芋羊羹みたいになっちゃいました・・・(苦笑)。
――(笑)。若松さんは先月誕生月だったそうですが、30歳を迎えて「こんな人になりたい」みたいな目標はあるんですか?
とにかく、つまらない人間にだけはなりたくなくて。自分がワクワクすることを追い求めて、常にそっちに舵を切れる人になりたいです。例えば、これまではバスケ漬けでできなかった海外一人旅にも挑戦したい! 母にハワイのよさを聞いてからハワイには絶対行きたくて、デフリンピックが終わって時間ができたら行きたいなって考えています。
――いろいろなお話をありがとうございました! 最後に、デフリンピックを楽しみにしている読者の方にメッセージをお願いします。
100年の歴史で初めて日本で、そして東京で開催されるとても貴重な大会です。デフバスケだけではなく、ぜひいろいろな競技を現地で観戦していただき、デフスポーツ、そしてデフアスリートの魅力を知ってもらえたら嬉しいです。
私たちも観客の皆さんに楽しんでもらえるプレーをお見せしますので、デフバスケ特有の空気感をぜひ会場で体感してください! 会場は大田区総合体育館です。一緒に歴史的な瞬間を盛り上げましょう!







Instagram:__yuzuw__
text by 開 洋美
photographs by 椋尾 詩



