
2025.08.07

2025.10.08
東京2025デフリンピック開幕まで50日を切った9月28日(日)、大会でも重要な役割を担う「手話通訳士」の魅力を紐解くトークセッション『ふたつの世界をつなぐ存在 ~手話通訳士の魅力~』を開催!
ろう者でありデフリンピック応援アンバサダーを務める川俣郁美さんをファシリテーターに迎え、第一線で活躍する手話通訳士の江原こう平さん、佐藤晴香さん、橋本一郎さんをパネリストにお招きしました。

今回のイベントでは登壇者4名全員が手話言語でトーク。それを対面に構える手話言語通訳が日本語音声へ通訳、さらにその音声を字幕に変換してモニターに投影する形で実施。
日常の通訳から国際大会の現場まで、普段は見えにくい“手話通訳士の舞台裏”やその専門性、やりがい、そして社会における重要性について語り合いました。
パネリストのお一人、江原こう平さんは、医療や司法などの場で、きこえない人・きこえにくい人と専門家を繋ぐ役割を担うコミュニティ通訳や、国の会見、テレビの通訳など約30年のキャリアをお持ちです。
なんと「令和」の元号を発表した記者会見の手話言語通訳も担われた方なのです。

手話通訳士の役割について江原さんは、「異なる言語を使う人たちの間で、言語をつなぐ、コミュニケーションをつなぐ、そして人と人とをつなぐ」ことだと語ります。
「きこえない・きこえにくい人ときこえる人では、情報のとらえ方や感じ方、そして身体感覚が違うんです」と佐藤さん。日本デフ水泳協会の手話言語通訳者としてチームの合宿や大会に帯同し、日ごろからデフスポーツの現場で活躍しています。
お互いの背景や環境の違いを認識し、その上で『つなぐ』ことを意識していると言います。
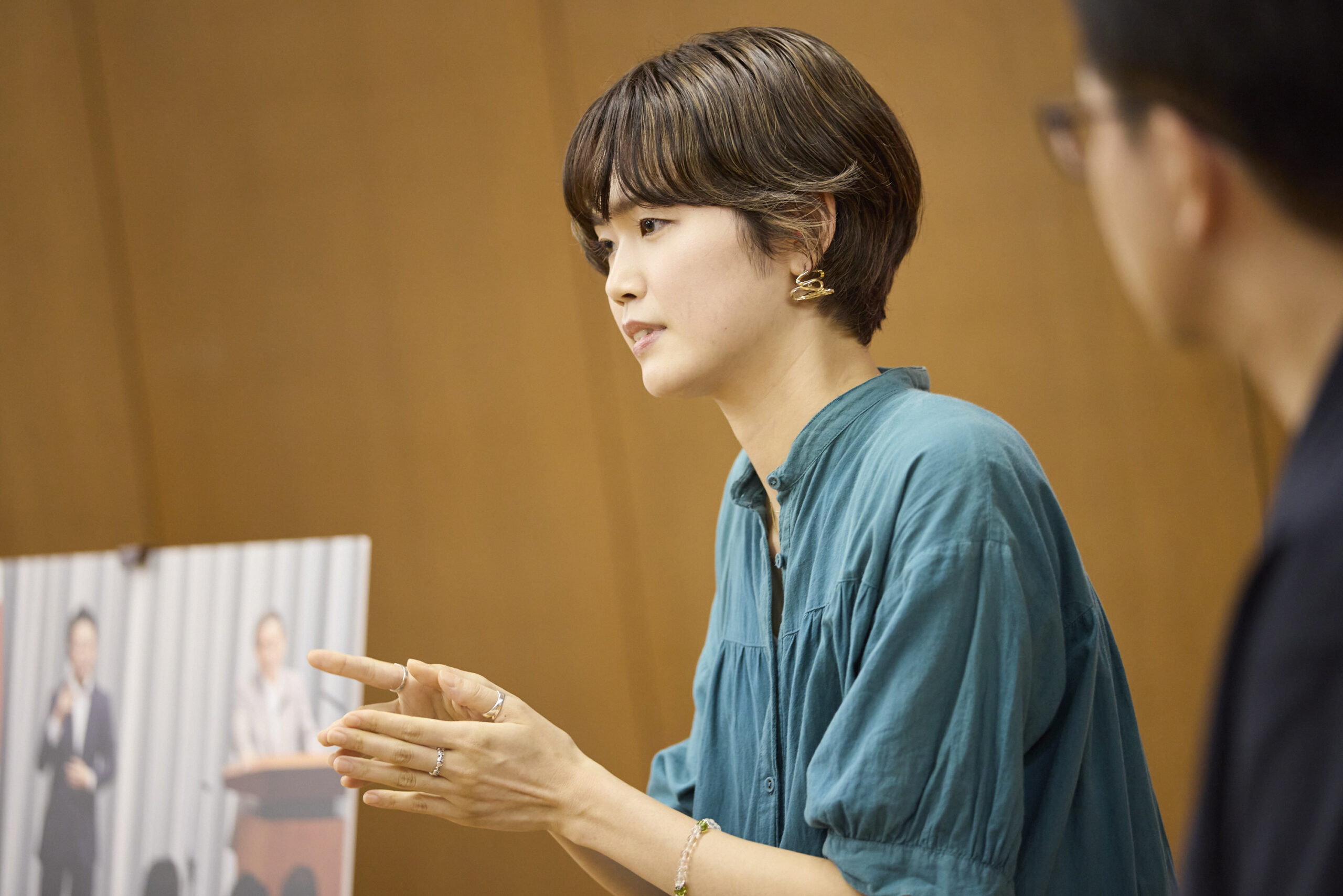
手話言語通訳を利用する立場として、「私は手話言語通訳の方に励まされることも多いんです」と川俣さん。きこえる人が手話言語通訳に話しかけるとき、慣れていない方だと、ずっと手話言語通訳の方を見て話してしまったり、手話言語通訳に答えを求めてしまったりすることも。ですがそのときに、「私の方を向いて話を投げかけてくれて、輪に入れてくれるとプロだなぁと嬉しく思います」とのこと。自身の立場を理解し、きこえない人とのコミュニケーションの環境づくりを行う存在であってほしい、と伝えました。

ろう学校や特別支援学校で教員を長年務め、“手話アーティスト”としても活躍する橋本さんは、「手話言語通訳を福祉の一環であるとか、黒いスーツの人などというイメージを取り払いたい。手話通訳士が、憧れの職業になるといいな」と想いを語りました。

デフリンピックが近づき強化合宿などの活動も佳境に入ってきているデフスポーツ界。このイベントの前にもデフ水泳の合宿に帯同していた佐藤さんは、「様々な立場の人が一斉に集まり、宿泊を伴う長時間の集団行動の中で、選手もスタッフもきこえる・きこえない・きこえにくいがバラバラ。皆が同じ情報がとれるように『場の調整』を心がけているが、本当に難しい」と現場のリアルを教えてくれました。
実際の練習の中では、きこえるコーチが自分の身体を使って指導する場面も。そのときには逐一通訳するのではなく、「それよりもしっかり見た方がわかりやすい」と、選手の視線を誘導する工夫を行います。そのために、コーチにも動くタイミングを調整してもらうなど連携してもらうことで、情報を円滑に、かつ効果的に得るための環境づくりにアプローチしています。

手話言語の社会的認知が広がる一方で、橋本さんは「まだまだ“想像力の欠如”によって手話言語通訳への理解や待遇面が変わってきていない」ことが課題であると言及します。イベントなどでの手話言語通訳の起用が増えてきているものの、その立ち位置や会場の照明によっては、手話言語を必要とする人の位置から見えづらくなってしまうことも。
起用する側にも、手話言語通訳がどのような機能を果たし、それゆえにどのようなポジションにレイアウトされるのが最適なのか、その理解の醸成が必要だと語ります。

また、待遇面に関して江原さんは「公認資格ができ、ここ30年で大きく変化したのは事実です。“ボランティア扱い”から仕事へと認知され、働き口は増えてきました」。メディアの影響などもあり、「今は手話通訳士になりたいという志を持って学びに来る若い人も増えてきているように感じる」と、全国各地で研修や指導を行う立場から得られた印象も教えてくれました。

手話通訳士のリアルな舞台裏が伺えた今回のトークセッション。いよいよ目前に迫るデフリンピックへの期待について伺うと、「まず、デフアスリートたちが障壁なく競技できる環境をつくりたい。それをきっかけに、障壁のない社会を作りたい。そのためには手話言語通訳者になりたいという人も増やしたいと考えています」と江原さん。
そして佐藤さんは、「ぜひ会場に来てほしいです。手話言語でコミュニケーションをとっている環境や、観る人も手話言語で会話したり応援したりする場にいることは貴重な機会。手話言語が分からない人がマイノリティーになる経験は面白いはずです」。その体験を通して、きこえない・きこえにくい人とつながりを、「デフリンピックが終わった後も形として残ってほしい」と想いを込めて伝えました。

橋本さんは、「教え子や友人がたくさん出場するので、会場に応援に行きまくります。通訳の仕事はしません! 毎日SNSで発信して、デフアスリートを応援する仲間を増やすのが僕の役割。子供たちが選手の姿を見て憧れる、希望をもって生きられる社会づくりにとても期待しています」と語りました。
「デフアスリートの熱戦の裏側には、それを支える手話通訳士がいます。手話言語の世界は魅力がいっぱい。これからもっと活躍の場が増えることを願っています」と川俣さんもメッセージを送りました。

デフリンピックの成功に欠かせない存在の『手話通訳士』。ぜひ会場で、彼らの活躍にも注目してみてください!
東京2025デフリンピック、11月15日開幕!!



